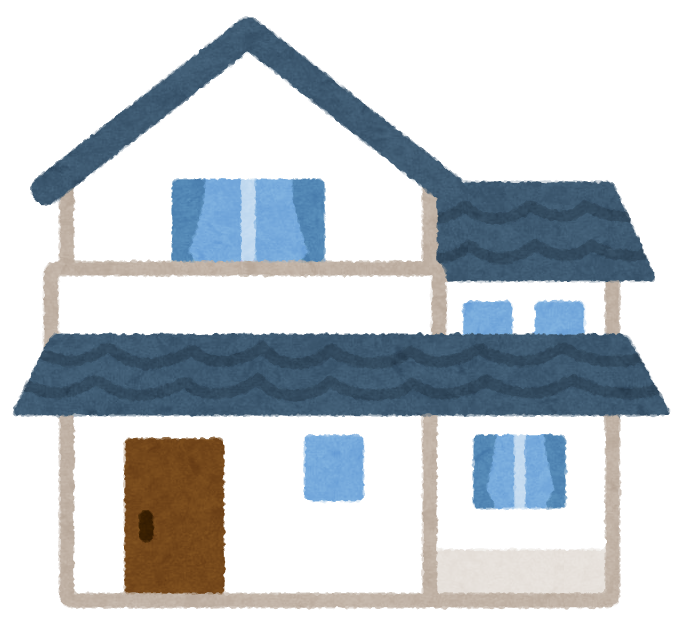既に所有している家を貸家として活用する際の注意点
不動産投資が活況を呈している昨今、相続した家や転勤、古くなり住まなくなった既に所有している家を貸家として活用する方が増えてきました。
物件をわざわざ買うよりは初期投資も少なく、放置するより賃料を得て税金の支払いに充てるといったことも出来るため、とても魅力的です。
しかし、他人に住居を提供する以上、責任も発生し、さらにいくつかの重要なポイントに注意する必要があります。
今回は、既存の家を貸家として活用するための注意点を、わかりやすく解説していきます。
1. 物件の状態をチェック&整備する
貸家として家を提供する前に、まずは物件の状態をしっかりと確認しましょう。
入居者が快適に暮らせるように、必要な修繕や改善を行うことが大切です。
これを怠ると入居者がいつまでも見つからない、せっかく入居しても修理対応に追われるといったことになりかねないので、注意しましょう。
設備の点検と修繕
古い物件の場合、空調設備や水回り電気系統に不具合が出ていることもあります。
漏水や電気のトラブルが起きないよう、専門業者に点検を依頼しましょう。
その上で、古い設備は事前に交換を行うことも検討しましょう。
また、各所内装劣化、腐食、屋根や外壁の劣化具合もチェックし、必要であれば修理を行うことをおすすめします。
安全性の確認
安全面も忘れずに確認しましょう。
特に、耐震性や防火、転落対策は重要です。
建物の過度な傾き、シロアリ被害の有無等は可能な限り確認し、見受けられる場合は専門業者などに相談しましょう。
住宅用火災警報器などの消防設備の設置をしないで貸し出ししている物件もありますが、山梨県では既存住宅も含めたすべての住宅に設置が義務化されています。
設置する場所も指定があるので、もし設置していない場合は適切な場所に事前に設置しましょう。
また、2階に部屋がある物件の場合は窓が過度に低い場合は転落防止用の柵の設置や階段に手すりが無い場合は手すりの設置など検討しましょう。
2. 賃貸契約書をしっかり作成する
物件の準備が整い、募集活動を経て、入居希望者が見つかった後は賃貸借契約書類の作成・契約を行います。
賃貸契約書は後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。
基本的には募集活動から契約書作成などの契約業務、引渡しまでを不動産会社に依頼することが大半ですが、貸主も契約の内容をしっかり把握しておくことが大切です。
入居者との契約内容を明確にすることで、双方が安心して契約を結ぶことができます。
契約内容の確認
- 賃料: 市場相場を参考に、適切な賃料を設定しましょう。家賃が高すぎても低すぎても問題が生じるため、慎重に決定することが大切です。
- 敷金・礼金: 敷金は退去時の修繕費用として、礼金はオーナー側に支払われる金額です。これらを地域相場に合わせて設定しましょう。
- 契約期間と更新料: 契約期間は通常2年が一般的です。更新料の有無や、更新手続きのルールを事前に決めておきましょう。
敷地の管理、ペットや喫煙に関するルール
住宅の場合、アパート等と違い敷地すべて入居者に貸し出すため、草刈りなどの庭の管理、浄化槽などの排水設備の維持管理をどちらが行うかなど明確にしておきましょう。
またペットを飼いたい入居者もいるかもしれませんが、ペット可かどうかの規定を契約書に明記しておくことが重要です。
喫煙に関するルールも設定し、トラブルを防ぎましょう。
3. 保証人や保証会社の利用
貸家を運営する場合、入居者が家賃を滞納するリスクがあります。
そこで、保証人を設定するか、保証会社を利用することが大切です。
おススメは保証会社の利用ですが、個人間ややむを得ない事情の場合は保証人を立てて契約する場合もあります。
また保証会社のプランによっては保証人を立てることもあります。
保証人の設定
親族や信頼できる友人を保証人に立てることが一般的ですが、その際には、支払い能力や人柄をしっかり確認しておくことが重要です。
トラブルがあった場合、きちんと対応してくれそうか等確認しておきましょう。
保証会社の利用
現在賃貸契約の多くで利用されているのが、保証会社を利用する方法です。
保証会社に依頼すれば、入居時の審査を行ってくれたり、入居者が家賃や退去時費用などを滞納した場合に代わりに支払ってくれるので、リスクが大幅に軽減されます。
仲介して売れる不動産会社にも確認して、保証会社の導入を検討しましょう。
4. 税金と確定申告を忘れずに
貸家を運営すると、家賃収入が得られますが、その収入には税金がかかります。
不動産を所有している以上は物件所在地によって様々な税金もかかります。
そういった各種税金は貸主が支払う必要があります。
税務面での管理をしっかり行わなければ、後でトラブルになりかねません。
主な例をご紹介します。
所得税と確定申告
家賃収入は「不動産所得」として扱われるため、確定申告を行い、所得税を納める必要があります。
収入から修繕費や管理費、固定資産税などを差し引いて、課税対象となる金額を算出します。
固定資産税
物件を所有している限り、毎年固定資産税がかかります。
物件の評価額に基づいて税額が決まるため、予めどの程度の税金がかかるかを確認しておくことが重要です。
5. 物件管理の方法を決める
貸家を運営する際には、物件の管理方法を選ぶ必要があります。主に「自主管理」と「管理会社への委託」の2つの方法があります。
自主管理
自分で管理する方法です。家賃回収や修繕手配、入居者とのやり取りなど、すべて自分で行うことになります。
メリットとしては管理費用がかからない点が挙げられますが、その分時間や労力がかかります。
管理会社に委託
管理会社に物件管理を任せる方法です。
管理会社が入居者募集から契約業務、家賃回収、修繕手配まで全てを担当してくれるため、手間を省くことができます。
管理費用がかかりますが、初めて物件を貸し出す方や手間を省きたい方、遠方に居住している方にはおすすめです。
6. 入居者選定とリスク管理
貸家を提供する際には、入居者選定が非常に重要です。信頼できる入居者を選ぶことで、家賃滞納やトラブルを避けることができます。
入居者の信用調査
入居者が家賃を滞納しないよう、信用調査を行うことが大切です。
過去の支払い履歴や収入状況を確認することで、リスクを軽減できます。
保証会社を利用する場合は保証会社が審査してくれるので手間を省けます。
保険の加入
入居者には入居時に必ず借家人賠償を加えた家財保険へ加入してもらうことが重要です。
また貸主側も、火災保険や地震保険、施設賠償や個人賠償責任保険などに加入することをおすすめします。
万が一の災害や建物での事故に備えることで、リスクを最小限に抑えることができます。
7. 入居者との良好な関係を築く
最後に、入居者との良好な関係を築くことが、貸家経営において重要です。定期的な点検やメンテナンスを行い、トラブルが発生した際には迅速に対応するよう心がけましょう。
定期点検とメンテナンス
定期的に物件を点検し、必要なメンテナンスを行うことで、入居者の不満やトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめ
既に所有している家を貸家として活用するには、特に事前の整備、リスク管理を徹底することが大切です。
入居者との良好な関係を築くことで、安定した収益を得ることができます。
しっかりと準備をして、長期的に成功する貸家経営を目指しましょう!
弊社では実際に貸し出しできそうかといった賃貸相談や賃料査定も無料で承っております。
お気軽にご相談ください!